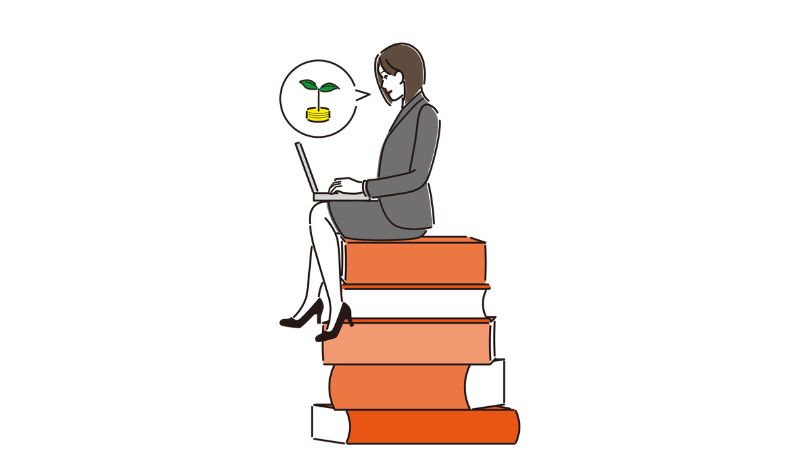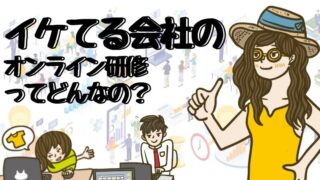はじめに
本記事では、リモート研修を成功させるための基本をまとめました。
コロナ禍でリモート化が進む現代のビジネスシーン。研修をオンラインで行う企業も増えています。しかし、リモート研修では熱気が生まれにくく、モチベーションが上がりづらいという声も聞かれます。
それらの対策として大事なのは、社員一人ひとりに研修を自分ごととして捉えてもらうことです。リモート研修の導入を検討している経営者または人事の研修担当者の方におすすめの記事です。
リモート研修の基本編
コロナによってリモート研修の導入を検討している企業が増えています。web上でも、リモート研修の成功事例を報告するサイトをよく見かけるようになりました。この章では、リモート研修の基本になる理論や事前学習について説明します。
1. 目的を考える際は、ゴールデン・サークル理論を活用

受講者の主体性を促すことを考える
研修の担当者に「なぜこの研修を実施するのか?」と質問すると、次のような答えが返ってくるでしょう。「新入社員を育てるため」「管理職の役割を理解してもらうため」「コンプライアンスの意識を深めてもらうため」など。
しかし、それらはすべて会社側の目線です。会社目線の目的が、受講者のモチベーションにつながるとは限りません。
人の行動は、「そうしなければいけないから」「そうしてもらいたいと言われたから」という理由ではなく、「そうしたいから」という理由によって生まれます。
つまり、受講者の主体性を促すには、受講者目線での目的を明確し、それを受講者に説明する必要があります。
目的を説明する際は、ゴールデンサークル理論を活用してみてください。この理論では、「Why(なぜ)」「How(どうして)」「What(何を)」のうち、Whyを出発点にして物事を説明していきます。
たとえば働き方改革についての研修を行うときは、
1 Why;人生の価値を高めよう
2 How;そのためにはワーク・ライフ・バランスを取るべき
3 What;じゃあ、業務の効率化で生産性アップが必要だよね
という順番で説明することになります。
「会社として働き方改革に取り組まなくてはいけないから」より、「あなたの人生がより豊かになるから」と説明されるほうが、研修に対して意欲的になるのは当然といえるでしょう。
2. 定性的な単位で受講者を選び、研修の目的を明確にしよう!

定量的に選ばれた受講者には能力やニーズにばらつきがある
新入社員研修や内定者研修、昇格者研修に管理職研修など、一般的な研修は、定量的な単位ごとに受講者が選ばれます。
しかし、定量的な単位では、受講者の中に能力やニーズのばらつきが生じてしまいます。ある受講者は熱心に取り組む一方、別の受講者は寝ている……。
という状況が発生するのも、受講者ごとに求めているものが違うからに他なりません。
定性的に受講者を選ぶと、研修目的も明確化しやすい
リモート研修は、受講場所を選ばないという特性から、部署などの壁を越えて受講者を集められるところも強みです。
「最近仕事にやりがいを感じない」、「結婚したばかりで、仕事と家庭のバランスのとり方がわからない」など、定性的な単位で受講者を集めて研修することも可能なのです。
ここまで研修の目的がはっきりしていれば、受講者も研修を受ける意義や目的を明確に理解し、主体的に臨めるようになります。
こういう研修をしてほしいなどと、社員から研修内容を公募するのも妙案です。研修に対し、社員がより主体的に行動するようになるでしょう。
3. 事前学習を徹底し、研修時間を有意義に!

リモート研修はアウトプットに適している
テキストや動画による学習は研修前に終わらせておきましょう。これはリモート研修のデメリットを解消するためです。
リモート研修はモニター上で顔が見えるとはいえ講師と受講者の距離が遠いので、座学にはあまり適していません。集中力が続きにくいのです。
そのため、インプットよりもアウトプットの機会として活用するほうが適しています。
リモート研修をアウトプットの機会にするためには、以下のような工夫が考えられます。
・事前資料から自分なりに意見をまとめて、研修時間内に発表してもらう
・役員クラスに参加してもらい、グループ対抗でプレゼンを競ってもらう
・講師による説明のあと、質問や討議の時間を多めに設ける
役員の参加も促し、全社的な雰囲気を出す
特に、役員クラスに参加してもらってプレゼン大会を開くのは、新入社員研修に効果的です。リモートならワンクリックで参加できるので、多忙な役員に対しても参加を依頼しやすいでしょう。
発表形式でリモート研修を行うと、発表者以外の受講者は聞き役に回ってしまいがちです。発言やメッセージを送信すると、他の受講者の邪魔になってしまうかもしれないと考えるからです。そこで、リモートアプリに付属する絵文字やスタンプ機能を活用しましょう。「ここをもっと詳しく聞きたいと思ったら、びっくりマーク」、「質問したいと思ったら挙手のスタンプ」など、リアクションに応じた絵文字・スタンプをあらかじめ決めておくと便利です。
4. リモート研修の外注は丸投げ禁止!外注先と自社とで認識をすり合わせよう

企業理念から逸れた研修は、総じて失敗と考えるべし
リアル型の研修からリモートへの切り替え対応が難航し、研修会社への外注を検討している企業もあると思います。このとき、外注先への丸投げは禁物です。
そもそも研修は、社員のスキル向上が目的ではありません。自分たちの会社が抱く理念(自社サービスで世の中を便利にしたい、ビジネスにイノベーションを起こしたい、顧客の生活をより豊かにしたい……)を実現するために必要な人材を育てることが目的です。
たとえ営業部署の成績が200%成長したとしても、それが企業理念に反する活動によるものなら、その研修は失敗です。
外注先と自社とで認識をすり合わせよう
つまり、すべての研修の前提にあるのは「企業理念」なのです。ゴールデン・サークル理論でいう「Why」の部分ですね。
そして、企業理念を最もよく理解しているのは、その会社で働く人たちです。だからこそ、外注するときは丸投げにせず、自社の企業理念をしっかりと伝えて、認識の齟齬がないようにしましょう。
より質の高い研修を行いたいなら、あらかじめ課題を抽出し、その解決につながる研修をしてほしいと依頼することがおすすめです。研修会社もプロとはいえ、限られたスケジュールの中で一からプログラムをつくっていくのは困難です。また、受講者目線での目的を考えたり、事前学習を徹底するなどして受講者のモチベーションを高めておくことも忘れないようにしましょう。
5. 過去の研修にこだわるな!リモート研修の最大の注意点

リモートに最適化された研修を実施しよう
最後にして最大のリモート研修の注意点。それは、対面で行っていた従来の研修を、そのままリモートで再現しようとしてはいけない、ということです。
対面で会話するときの空気感をオンライン通話で再現することが難しいように、対面式の研修をそのままリモートで行おうとしても、おそらく失敗するでしょう。
それよりも、たとえ従来の研修とはまったく違う形になってもいいので、リモートに最適化された研修を実施することが大切です。
おさえておきたいリモート研修の特性とは
最後に、リモート研修の特性を紹介します。
・移動の制約が少ない
→役員など、リアルでは参加ができなかった人物をオブザーブ参加させやすい。
・場所の制約が少ない
→参加人数に上限がない。動画視聴の研修ならリモートは一斉に見せることが可能。
・データの蓄積、活用がたやすい
→リモートなら、詳細なデータを入手できる。
受講者がいつ学習したのか、どのくらいの時間がかかったのか、どのようなコメントをしたのか、テストは何点だったのか、などといったしかもデジタルデータとして取得できるので、紙ベースに比べて管理や分析も簡単です。収集したデータの活用方法としては、社員一人ひとりに最適な学習を提供するなどが考えられます。
おわりに
リモート会議の事例調査中に感じたのは、多くの企業がやむを得ずリモートを導入しているということ。仕方なく取り入れたという姿勢が「リアル型研修と同等の成果を出せた」ことで満足しきってしまう結果につながっているのでしょう。本当は、リアルとは違った側面、あるいはそれ以上の成果をもたらすことも可能であることに気づいてください